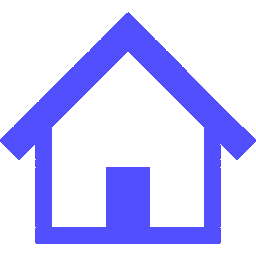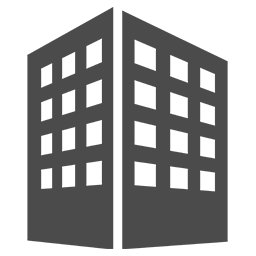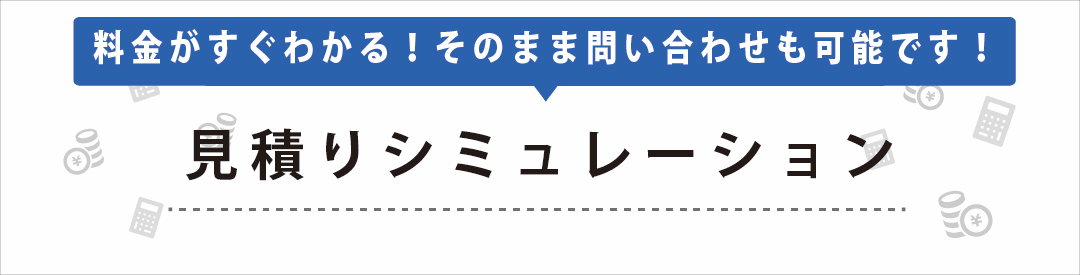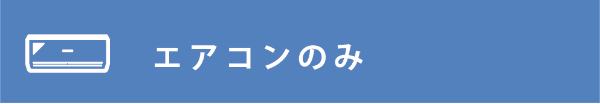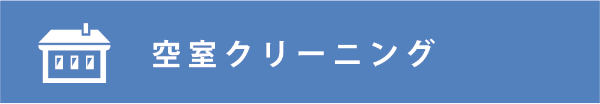大掃除
更新日:2024年10月02日
天井
天井は普段ケアしないだけに、案外しっかり汚れている物です。
はたきを掃除機の筒の先に付けてなぞるだけでごみはとれます。
あとは水拭きすればOKです。
天井を拭くときは、天井と頭の間に握りこぶし一つくらいの距離をとれるよう椅子や脚立を用意します。
クロス壁
クロス壁の汚れは、布クロスの場合、繊維の隙間にホコリが入っているので、はたきで表面の汚れを取った後固く絞った雑巾で手早く拭きます。
しみにならないよう薬品を使わないほうが無難です。
ビニールクロスの場合は、水拭きして汚れが取れなかったら、洗剤スプレーを使います。
こびりついた汚れには、ブラシ類を使います。
スペースが狭ければ歯ブラシを、広ければたわしを、柔らかい壁紙のときはたわしをタオルでくるんでこすってみましょう。
カーペット
カーペットの汚れを簡単に、しかもきれいに済ませたいときは、両面テープのローラーと手動式のフクバホーキーが便利。
カーペットに絡みついた髪の毛や糸くず、ペットの毛などを見逃さず取った後掃除機をかければ完璧です。
徹底的に掃除したい場合は絨毯クリーナーを使います。
泡状の洗剤をカーペットの上にうっすら雪が積もった程度にまき、ブラシでこすります。
泡はカーペット内の汚れを吸い込んで粉になり、それを掃除機で吸い取ります。
カーペットにできた原因不明のしみは、まず水で、それがだめならお酢を薄めたもので丁寧にこすってみます。
たいていのしみはこれでとれるはずです。
畳のお手入れ
畳のお手入れは、乾拭きが原則ですがどうしても時間がたつうちに薄汚れてきてしまうので、そのときはお酢を使ってリフレッシュさせます。
バケツ半分くらいの水に、お酢をすこし加えたもので雑巾がけをします。
お酢には黄ばみをとる漂白効果があるので、心持ち元の美しさにもどります。
食べ物の汚れ
カーペットや畳にこぼした食べ物の汚れは、ちゃんと処置しないとしみになってしまいます。
シミを残さないための汚れの落とし方を覚えておきましょう。
汚れには油性のものと水性のものがあり、やっかいなのは油性の汚れです。
ベンジンか消毒用アルコールで油分を落とし、色素はお酢や洗濯石鹸の水溶液で落とします。
油性の汚れの中でも厄介なのがカレーです。
スパイスが多いので色素も複雑です。
ベンジンで油分を落とし、色素はベンジンが蒸発した後、石鹼液かお酢を含んだ布でたたいて抜きます。
チョコレートは油分が含まれていますが、多量ではないので消毒用アルコールを含ませた布でつかみ取るようにして油分を取り除けば汚れは落ちます。
色素が残る場合は、石鹸水を含んだ布で拭き、水拭きすればOKです。
ケチャップは布でつまむようにしてあらかた汚れを取った後、お酢を使って赤い色素を落とします。
お酢には漂白作用があり、ケチャップのような色の濃い汚れには効果的です。
あとは水を含んだ布で叩くようにしてお酢を吸収させます。
醤油やコーヒー、紅茶や緑茶、みそ汁などの水性の汚れは、こぼれた直後ならとにかく乾いた布で吸い取ります。
シミが残るようなときは、石鹸液を含んだ布で叩くようにして汚れを取りましょう。
牛乳やヨーグルトなどの乳製品は、タンパク質が落ちていないとあとで黄ばみますから、アルコールを含んだ布で抑えて取り除き、つぎにタンパク質を分解する酵素入り洗剤の水溶液を歯ブラシにつけてこすり、30分くらいそのままにしておき、最後に水を含んだ布で叩くようにして吸収します。
油性の汚れにも水性の汚れにもあてはまらないガムがこびりついたら、氷をビニール袋に入れてガムの上に置きます。
5分くらいで固くなるので一気にはがします。
マニキュアは乾いた布で叩くようにして吸い取り、残りを除光液かアセトンを含んだ布で叩くようにして色素を取り除きます。