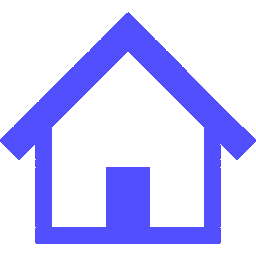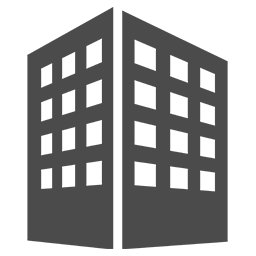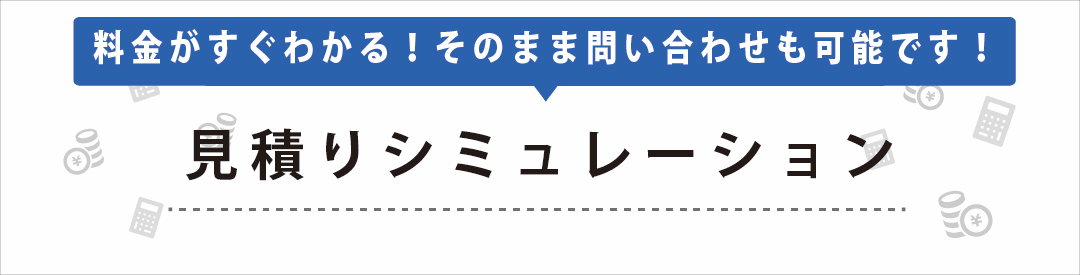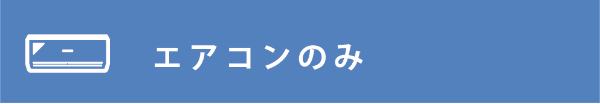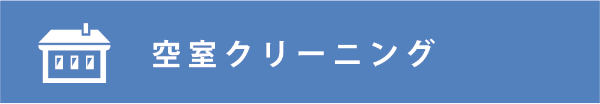石鹸について1
更新日:2024年09月05日
石鹸とは❓
石鹸は脂肪酸とアルカリでできた物質です。
原料は動物や植物からとれる油脂。これらの油脂をアルカリと混ぜあわせて加熱し、化学反応をさせて製造されています。
石鹸にもいろいろなタイプがありますが、固形・粉状のものは脂肪酸ナトリウムで作られ、主に浴用石鹸や洗濯石鹸などに使われています。
液状・ジェル状のものは脂肪酸カリウムで作られ、ハンドソープや台所用液体石鹸として利用されています。
また、石鹸は界面活性剤の一種です。界面活性剤は水と油のどちらともなじむ性質があり、本来ならば反発しあうはずの両者を混ぜ合わせる働きをします。
石鹸が髪や体の皮脂汚れを落とすことができるのは、この界面活性剤によるものです。
石鹸の歴史
固形石鹸が日本で製造されるようになったのは、明治3年頃のこと。
当時の石鹸は、牛脂とナスの灰汁を飴状にしたものをハマグリの殻に入れて売ったとか。
その後、横浜で民間の石鹸製造の始まりとなり、明治初期には石鹸製造業が数多く起業されました。
一般の人も安価に石鹸を入手できるようになったことで、洗顔・入浴・洗濯に石鹸を使うことが普及していきます。
石鹸の持つ洗い流すという意味から、快気祝いや香典返しなどの贈り物としても定番になり、暮らしに欠かせないアイテムとして今日まで至っています。
石鹸の種類
石鹸の種類は本当にさまざま。
経済産業省の統計では、洗浄剤の種類について、身体を洗うものと身体以外のものを洗うものとに分類されています。
そのうえで、身体の洗浄剤を皮脂用と頭髪用に分類し、皮脂用を浴用固形石鹸、手洗い用液体石鹸、これらと別に洗顔石鹸やボディソープについては洗顔・ボディ用身体洗浄剤として表示しています。
この他の衣料用、台所用の洗浄剤は、石けんとひとくくりにしています。
また、一般的に身体用にはボディソープ、手洗い用にハンドソープという名称も定着しています。
これらは用途や見た目の形のほか、製法や科学的な特徴をもとにつけられた呼び名も混ざっていて、法律によっても対象定義が異なるので少し複雑です。