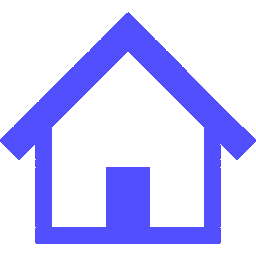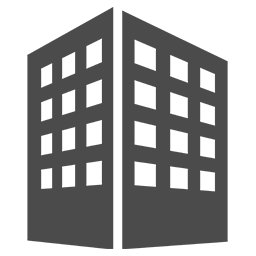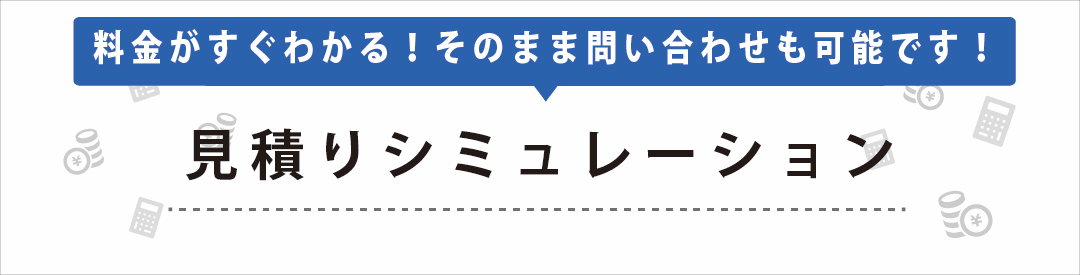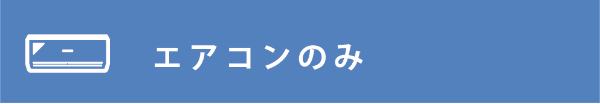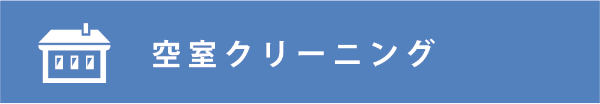江戸時代の掃除
更新日:2025年02月10日 その他コラム
江戸時代の掃除は、現代とは異なり、道具や方法に独特の特徴がありました。当時の人々は清潔を保つことを重視しており、特に寺社や武家屋敷、町家などでは定期的な掃除が行われていました。以下、江戸時代の掃除について詳しく説明します。
1. 掃除の習慣と考え方
江戸時代の人々は「掃除=心の清め」と考えており、単なる家事ではなく、精神的な意味も持っていました。特に武士階級では「武士道」の一環として、掃除が重視され、寺院や武家屋敷では「毎朝の掃除」が習慣化していました。
また、庶民の間でも掃除は日常的に行われ、家の中だけでなく、家の前の道路まで掃除するのが当たり前でした。これは、江戸の町を清潔に保つための共同意識の表れでもあります。
2. 江戸時代の掃除道具
当時は電気掃除機などはもちろんありませんが、自然素材を活用した掃除道具が使われていました。
① ほうき
シュロのほうき(柔らかい):畳や床の掃除に使用。
竹ほうき(硬め):庭や屋外の掃除に使われた。
② ちりとり
「ちりとり」は、竹や木で作られたものが一般的。
「はばき」と呼ばれる塵取り用の道具も使われた。
③ 雑巾(ぞうきん)
木綿布を再利用し、水拭きや仕上げ掃除に使われた。
現代の雑巾掛けのように、床や柱を丁寧に拭いていた。
④ 灰(はい)
ぬか袋や木灰を撒いて、埃を抑えながら掃除する方法があった。
掃除後に灰を払えば、埃が舞いにくくなるという工夫。
⑤ 竹製のハタキ
現代のはたきの原型で、埃を落とすために使われた。
3. 掃除の流れと方法
① 毎朝の掃除
武家屋敷や商家では、日の出とともに掃除を始めるのが習慣でした。特に家の外観を清潔にすることが重視され、玄関前の掃き掃除は欠かせませんでした。
② ほうきで掃く
まずはほうきで床や畳の埃を掃き出します。土間(どま)や屋外では竹ほうきを使い、細かい部分はシュロのほうきを使っていました。
③ 雑巾がけ
畳や板の間は、濡れ雑巾で拭き掃除。夏は乾拭き、冬はお湯で絞った雑巾を使うこともありました。
④ 庭や道の掃除
町人の家では、自分の家の前の道も掃除するのが常識でした。特に商家では、店の前を毎日掃除して清潔さを保ち、お客様に良い印象を与えるようにしていました。
4. 江戸の町とゴミ処理
江戸時代のゴミ処理システムは意外と発達しており、「リサイクル文化」が根付いていました。
① ゴミの再利用
紙屑は紙漉き職人によって再利用され、新しい紙に生まれ変わった。
壊れた陶器や金属製品も職人によって修理され、長く使われた。
食べ物の残りは家畜の餌や堆肥として活用。
② 汚物処理
江戸では「下肥(しもごえ)」と呼ばれる肥料として、人糞や動物の糞を回収し、農村で活用する仕組みがありました。これは「糞尿売買」として経済活動の一環にもなっていました。
5. まとめ
江戸時代の掃除は、自然素材を活用した道具と知恵を使い、環境にやさしい方法で行われていました。また、家の内外を清潔にすることが社会的なマナーとして根付いており、現代の「エコ意識」や「整理整頓の習慣」にも通じるものがあります。
江戸の人々の暮らしの知恵を参考にしながら、現代の掃除にも活かせるアイデアが多くあるかもしれませんね。