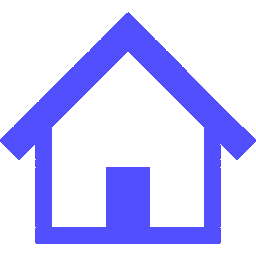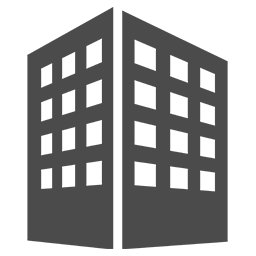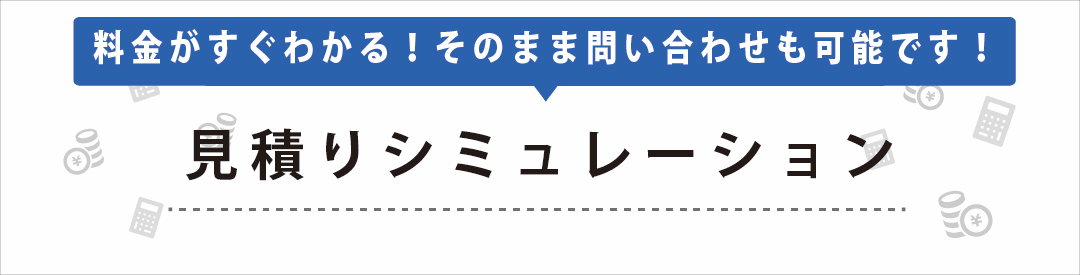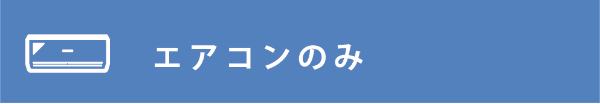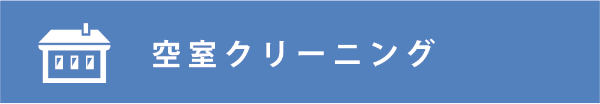エアコンの仕組み
更新日:2025年04月21日 ご家庭向け
なぜエアコンは空気を冷やしたり暖めたり出来るのでしょうか。
暑い夏でも寒い冬でも快適な室温にしてくれるエアコンの仕組みや構造について分かりやすく解説します。
エアコンは、熱は高温から低温に移動する、圧縮すると冷媒が高温になる、減圧すると冷媒が低温になるといった自然の性質を活かした仕組みで部屋を冷やしたり、暖めることができます。
冷房と暖房運転では、それぞれ真逆の動きをします。
冷房の仕組み
取り込まれた室内の空気の熱が冷媒に乗り、圧縮機で高温、室外機の熱交換器で熱を奪われ液体に変わります。
その後、室内機に戻された冷媒が空気の熱で蒸発し、気体へ変化します。
気化熱の原理により、液体が気化するときに熱を吸収され熱を奪われた冷気が室内に排出されます。
室内の空気に含まれる熱が熱交換器に取り込まれた後、配管内の冷媒に乗せられます。
熱を乗せた冷媒は、室外機に送られ圧縮機で圧力をかけます。
圧縮されることで冷媒の温度が上昇し、高温の気体となります。
高温・気体の冷媒は、室外機の熱交換器を通過するとき、ファンによって熱を外へ放出します。
熱交換器で冷媒は熱を奪われて液体になります。
減圧機で減圧すると、分子の距離が広がり膨張します。
膨張によって冷媒の温度は低下します。
低温の液体になった冷媒は、室内機に送られます。
室内機の熱交換器を通過して気体となり、冷たい風を吹き出します。
注射の前にアルコールで腕を消毒すると冷っとしますが、その理由はアルコールという液体が蒸発して気化する際に、腕の熱を奪うためです。
エアコンで空気が冷えるのも同じ理由です。
反対に、気体が液体になるときには周囲に放熱します。
暖房のしくみ
室外機の熱交換器が外気の熱を冷媒に移して圧縮。
高温の気体になった冷媒は、室内機の熱交換器に運ばれて暖気をだします。
気体が凝縮し熱を奪われた冷媒は、液体となり減圧され室外機へ循環し、冷えた熱を室外に放出します。
室外機の熱交換器で取り込まれた空気の熱が、配管内の冷媒に乗せられます。
熱を乗せた冷媒は、圧縮機で圧力をかけることで分子の距離が近くなり、冷媒の温度が上がります。
高温の気体となった冷媒は、室内機の熱交換器へと移動し、熱を手放して液体になります。
手放した熱は熱交換器で温風となり、暖かい風を吹き出します。
熱が放出された冷媒は室外機の減圧機で減圧されます。
圧力が低下することで冷媒は低温の液体となります。
冷媒は、大気の熱を取り込んで気体となり、室外機のファンから冷たい風を放出します。
冷房と除湿の違い
部屋の温度を下げる冷房と、温度を下げる除湿は実は同じ仕組みで働いています。
冷たい空気を広くいきわたるようにファンを動かす冷房に対して、除湿は体感温度の低下を感じさせないようにファンの動きを極力制限します。
上位グレードのエアコンは、温度の低下を極力少なくした除湿方式を採用している機種もあります。
また、グレードが高くなるほど消費電力を抑えた省エネ性能も高くなる傾向があります。
冷媒ガスとは
室内機と室外機は2本の配管でつながっていて、配管の中を冷媒が循環しています。
冷媒ガスは、空気の中にある熱を乗せて運ぶ役割を持っています。
冷媒は熱交換器を通って圧縮されると高温になり、減圧されると膨張し分子同士の距離が開くため低温になります。
冷暖房運転中に室内機と室外機を常に循環し、熱を乗せて運ぶ専用のガスが冷媒となります。
室内機の部品名称と役割
通風路
送風ファンの背面側にある風の通り道です。
送風ファンの気流方向を決める役割があり、ケーシングと呼ばれるパーツで構成されます。
フラップ
エアコンの吹き出し口に付いている板状の部品で、ルーバーと呼ばれます。
上下左右に動くことで空気の流れや風向きを調整する役割を担います。
送風ファン
筒型の形状をしたパーツで、回転することでエアコン内部の風が室内に循環します。
ファンが回転することで冷房時は冷たい空気を、暖房時は暖かい空気を部屋に送ります。
熱交換器
熱を交換したエアコン内部の空気を冷やしたり暖めたりする役割を担います。
温度調整を行うエアコンの心臓部にあたるパーツです。
ドレンパン
熱交換器のすぐ下にある横長の排水トレーです。
冷房時に熱交換器に付着して流れてきた水蒸気の受け皿となります。
フィルター
空気中の不純物をろ過したり、虫や花粉が侵入するのを防ぎます。
エアコン内部を清潔に保つ役割があります。
エアコンの能力を最大限引き出すために
室内機と室外機はなるべく近い位置に設置する。
エアコンを新たに設置する場合に気を付けたいのは冷媒配管の距離です。
例えば、2階に室内機で1階に室外機があるなど、冷媒の配管距離が長くなると熱が損なわれやすくなります。
熱効率が落ちると、ガス追加補充や長時間の真空引きなどが必要となります。
室内機と室外機は、できるだけ近い位置に配置することでエアコン本来の能力が発揮しやすくなります。
室外機周辺の環境を整える
暑さの厳しい夏場に直射日光が当たると、室外機本体が熱を持ち、能力が大幅に低下してしまいます。
室外機は日陰で稼働する方がその能力を発揮しやすくなります。
直射日光が当たる場所に室外機がある場合は、離れたところに植木を植えたり、よしずをたてかけたりするなどして、日陰を作ってあげるのも効果的です。
室外機の吹き出し口の前に荷物を置かない
冷房運転中は部屋の中の熱い空気を、暖房運転中は冷たい空気を室外に放出します。
そのため、風が吹き出す前方やその周囲に物を置いたりカバーで覆ってしまうと、稼働効率が低下してしまいます。
室外機の前は、空気の通り道として十分なスペース確保が必須です。
外壁との隙間に十分なスペースを確保する
室外機は後部から外気を取り込み、前方に空気を吐き出す仕組みとなっています。
設置時に適正の離隔距離を確保されていても、落ち葉などが後部に積もり吸気を阻害しているケースもあります。
室外機の後部の吸気を邪魔している物は無いか、定期的に確認してください。